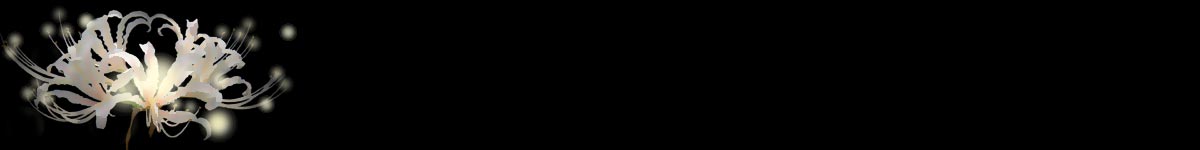
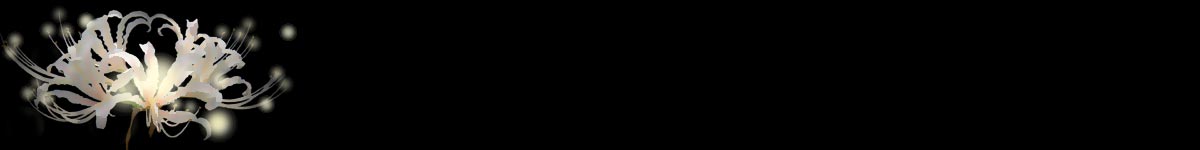
| 泡沫の約束 (どうしてこいつじゃなきゃいけなかったんだろう。でも……) 微かに震えている真弘の腕の中で、同じように体を震わせている後輩を見つめながら、真弘はやるせない気持ちになった。 怖いか、と問いかければ、気丈にも「怖くない」と答えるけれど、震えまでは誤魔化しきれていない珠紀の髪を、真弘は指に絡めた。 絹のようにさらりとした髪は、少し力を緩めただけで、真弘の指から零れ落ちていこうとする。 痛くないように気を遣いながら指に絡めた髪に、真弘はそっと口づける。 冷たい感触が、熱を持ったように熱い唇に心地好かった。 「珠紀」 珠紀を抱きしめる腕に力を込めながら、真弘は泣きたいような気持ちで言葉を唇に乗せた。 「――こんなに怖い目に合ってるお前に言うのは、なんだけどよ。珠紀、俺はさ、お前が玉依姫で良かったって思う」 真弘がそう言うと、珠紀の震えが止まった。 おずおずとした仕草で、真弘の背中が抱き返される。 「わたしも……」 小さな声がぽつりと落とされたけれど、その音はあまりにも小さすぎて、真弘の耳には届かなかった。 「聞こえねぇぞ」 からかうように「いつもの威勢の良さはどうしたよ?」と続けていると、ぐい、と、真弘の胸が押された。 抱きしめていた珠紀の温もりが、遠ざかる。 それを残念だと思いながらも、珠紀の顔が見られるから、まあ、別にいいかとも真弘は思った。 拗ねた顔の珠紀が、真正面から真弘を軽く睨んでいる。 やっと、真弘が良く知っている珠紀の表情が戻ったと思いながら、真弘はその表情を見つめていた。 「わたしも、真弘先輩が守護者でよかったって言ったんです!」 まるで叫ぶような口調で放たれたその言葉に、真弘は驚いた顔になった後、口元を綻ばせた。 そんな風に言ってもらえるとは、思わなかった。 守護者としての覚醒の方法を、ずっと黙っていた。ずっと贄の儀のことも黙っていた。 なにもかもを知っていながら、なにも言わずにいたのに。それでも真弘が守護者で良かったと、そんな言葉をもらえるとは思っていなかった。 ああ、そう言えば、キスしたときも、抱きしめたときも、突っ撥ねられなかったな、と、今さらのように思いだしていると、ふっと、珠紀の顔が悲しそうに歪んだ。 今にも泣き出しそうな顔で、 「……守護者だったばっかりに、贄として封印をしなきゃいけないって言われていた先輩に言う科白じゃないですよね」 そう呟いた珠紀の体を、真弘はもう一度抱き寄せた。 「バカ」 胸に溢れる気持ちを言葉にできなくて、いつものように悪態しか口にできないもどかしさが、腹立たしい。 本当にバカなのは自分だと思いながら、 「だったら、お互いさまじゃねぇか」 と軽い口調で真弘は言った。 ふっと、腕の中で緊張が緩む。 抱きしめた細い体が、力を抜いて、弛緩した。 「真弘先輩」 「うん?」 「先輩のこの羽、綺麗ですね。手触りが気持ちいい……」 「そうか? ……気持ち悪くねぇか?」 「平気ですよ。真弘先輩、そんなこと気にしてたんですか? なんだか先輩らしくないですよ。いつもの悪役笑いで「ヒーローっぽいだろ」とかなんとか言うほうがらしいですよ」 「なんだ、その悪役笑いってのは」 顔を顰めて言うと、たまきがくすくすと笑った。 「だって、真弘先輩の笑い方って、ヒーローよりも悪役みたいですよ」 「マジか?」 「マジです」 「うわー、なんっか、へこむぞ」 よりによって悪役かよ、と、深く溜息をつけば、珠紀の笑い声が大きくなった。 可笑しそうに笑い続けている珠紀を抱きしめたまま、真弘はもう一度、深い溜息を落とした。 ひとしきり笑って満足したのか、笑いをおさめた珠紀が、 「真弘先輩がどんな姿だって、わたし、好きですよ」 不意に真面目な口調になって、そう言った。 吐き出した吐息の震えを、真弘は誤魔化すこともできなかった。 たった数ヶ月、一緒に過ごしただけで。 この村のシステムも、住んでいる人間の感情も、なにも――なにひとつ解っていないくせに、そう言う科白を簡単に言うな、と、そう言ってやりたくなる。 その反面、なにも解っていないからこそのその科白に、救われる。 守護者としてではなく。異端の者としてではなく。珠紀が知ってくれた「鴉取真弘」という人間を、認め、肯定し、好意を寄せているとはっきりと判るその科白に、不覚にも泣きたいような気持ちになった。 ずっと、その言葉を求めていたのだと自覚した。 珠紀がくれた言葉は、真弘が言って欲しかった言葉だった。 たぶん、真弘だけじゃなく、守護者全員が欲している言葉。 守護者だと言い、遠巻きに畏怖の対象として見るのではなく、一個人として見て欲しかった。 接して欲しかった。 真弘たち守護者が、半分とはいえ妖の血を引き継ぎ、人ならざる力を持っていたとしても。 守護者であることを強く自覚してから、諦めていた言葉を珠紀から言ってもらえて。 この嬉しさを。幸福を、言葉や態度に代えて伝えてみたとしても、珠紀にはすべて伝えられない。 伝えきれない。 きっと、伝わらないだろうと、真弘は思った。 泣きたいような気持ちになりながら、それでも。 たとえ伝え切れなくても。伝わらなくても。 強く抱きしめて返すだけじゃなく。 「ありがとう」という言葉を唇に乗せ、音にするだけじゃなく。 それだけじゃ足りない、この想いや嬉しさのすべてを、誓いの言葉に代えて、真弘は言った。 「珠紀のことは、この真弘様が、全身全霊をかけて守ってやるよ。どんなことからも、さ」 いつもと変わらない口調で、軽くそう言って真弘は笑ったつもりだった。 けれど、目の前の珠紀の顔が泣き出しそうに歪んでいるのを見て、ああ、自分は笑うことに失敗したんだと、真弘は自嘲に顔を歪めながら思った。 誰より強く生きたいと願い、思いながら、それでもそれを選べない真弘の言葉は。 叶えられない約束。誓いの言葉が、珠紀を深く傷つけたのだと思うと、ただ、哀しかった――――。 END |
原○集の、真弘先輩の描き下ろしイラストから、イメージ。
インスピレーションで書いたの、丸判りです。すみません。
ストーリー、なさ過ぎだよ(涙)。
とりあえず逃亡途中のパラレル話、って感じで。